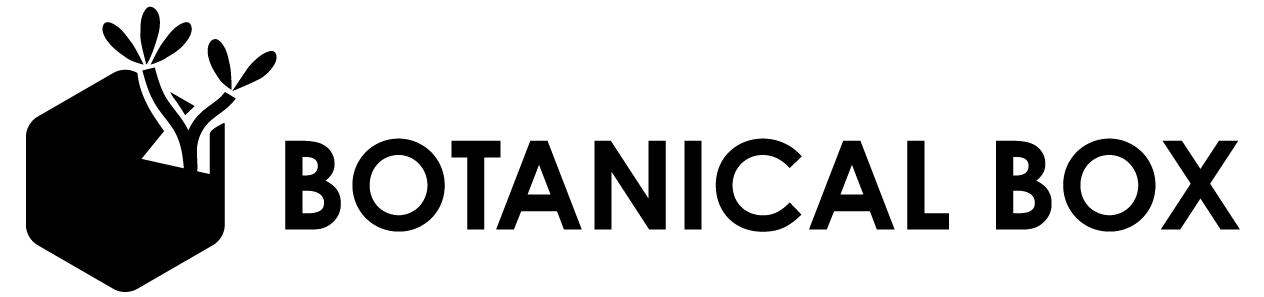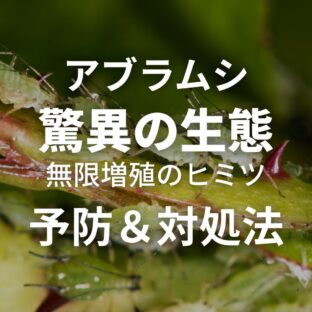【アブラムシ】驚異の生態|予防法と対処方
園芸をする中で、最も触れる機会の多い害虫にアブラムシがいると思います。
身近なアブラムシですが、実は驚異の生態をもっています。今回はそんなアブラムシの生態と、予防法、対象法などを紹介します。
アブラムシの脅威の生態
意外と思われるかもしれませんが、アブラムシはセミやアメンボと同じくカメムシの仲間です。カメムシの仲間に共通しているのは、ストロー状の口で植物や獲物の汁を吸うという点です。そのためアブラムシは吸汁(きゅうじゅう)害虫と呼ばれます。アブラムシの種類ですが日本では700種類以上が確認されています。
名前の由来ですが
江戸時代に、ハギの葉に付いたアブラムシをすり潰して頭髪に塗り、髪をテカテカに光らせる遊びが子供たちの間で行われていたとされます。この遊びが「油虫」という呼び名の由来になったという説があります。
アブラムシに悩まされる原因として、どこからともなくやってきて爆発的に増殖するというものがあります。これはアブラムシがメスだけの単為生殖を行えるためです。つまり、子を産むのにオスが必要なく、雌が1匹いれば増殖できるのです。また、アブラムシは通常、卵ではなく直接子供を産みます。1匹のメスは約1ヵ月生き、1日に約5匹の幼虫を生みます。その5匹がそれぞれ毎日5匹産み、、、を繰り返していくと、1ヵ月で1匹のメスから約1万匹まで増殖します。これがアブラムシが爆発的に増える理由です。
爆発的に増えたアブラムシのコロニー(群れ)が飽和すると、雌はなんと羽の生えた幼虫を生みます。こうして羽の生えた個体は風に乗り新天地を目指します
アブラムシの適温は約20~25℃で冬を除いた春~秋まで活動可能です。冬には死んでしまうのですがここからがアブラムシのすごいところ。秋も深まり生存の危機にさらされたメスのアブラムシはなんとここでオスを産みます。そしてオスと交尾して生まれるのは幼虫ではなく「卵」なのです。卵の状態なら冬を越すことが可能なので、冬にすべての成虫が死んでしまっても、翌春卵から孵った1匹のメスからまた増殖が始まります。
アブラムシの被害
ここからはアブラムシがもたらす被害を紹介します。
最初にアブラムシを吸汁害虫と紹介したように、アブラムシに吸汁された植物は栄養分が奪われ弱っていきます。躯体的な症状としては、葉が黄色くなったり萎縮したりします。新芽を吸汁されると「虫コブ」と言って葉が縮れたり、デコボコができたりします。虫こぶは植物の見た目が悪くなるのはもちろん、光合成の働きも落ちてしまいます。
二次被害として、アブラムシの尿が原因となって起きる「すす病」があります。アブラムシの尿は糖分をたっぷり含んでおりベタつきます。それが葉や土壌に溜まりカビが発生することによってすす病を引き起こします。すす病は進行するにしたがって葉全体が黒くなっていき光合成を阻害します。その結果植物が弱り、最悪の場合枯れてしまいます。
このほかにもアブラムシは、モザイク病を引きおこるモザイクウイルスを媒介することがあります。
被害にあいやすい植物
被害にあいやすい植物は、アブラムシが吸汁しやすい薄い葉をもった植物です。葉以外にも、細い茎や柔らかい枝を伸ばす植物にも付きやすいです。黄色に寄ってくる習性もあるので黄色い花を咲かせる植物も注意が必要です。またアブラムシは植物のアミノ酸成分を好んで吸汁するため、窒素分の多い肥料を与えるとアブラムシを引き寄せやすくなるようです。環境的な要因としては風通しが悪く、日陰になる場所を好みます。
自然界ではよく菜の花の茎にびっしりとアブラムシが付いているのを見かけます。
アブラムシの対策・予防
いろいろな害をもたらすアブラムシですが1匹1匹の力は弱いので、適切に対処すれば植物が枯れてしまうという場合は稀です。
では対策法予防法を1つずつ見てきましょう。
・木酢酸
直接アブラムシを殺す効果和ありませんが、植物の表面のクチクラ層を強化してアブラムシに吸汁されにくくなる効果があります。また木酢酸の独特の臭いに忌避効果があるとされています。木酢酸はアブラムシを見つけた後ではなく、日ごろから定期的に撒いておくことで効果を発揮するものと考えてください。
・粘着テープ
アブラムシが黄色に寄ってくる習性を利用した粘着テープ(捕虫テープ)で物理的に捕虫する方法です。すでに発生しているアブラムシにはあまり効果がないかもしれませんが、羽の生えたアブラムシやってきた際に効果を発揮します。これも予防的な意味合いが大きいです。捕虫テープはアブラムシ以外の虫のたくさん捕まえてくれるため、ハウス育成ではとても便利なアイテムです。
・オルトラン
予防法としては最もメジャーで効果も高いのがオルトランです。主に粒剤タイプを使用し、土に混ぜるか表土に撒くという使い方です。アブラムシに対する効果は約1ヵ月持続し、使用料は1鉢につき1~2グラムです。多肉植物や塊根植物の場合、植物に対して小さめの鉢を使用することも有るので撒きすぎには注意しましょう。植物自体にダメージを与えてしまいます。
・ベニカスプレー
こちらはすでに発生してしまったアブラムシに対して使います。大量発生している場合は数日おきに何回か使用しますが、これも使いすぎは植物にダメージを与えます。いざアブラムシが発生した時の対処として用意しておき、できれが事前の対策で発生を抑えるのが望ましいです。アブラムシに対する効果は1ヵ月とされていますが、個人的にはそこまで長くないかなと感じることも。
まとめ
以上がアブラムシの脅威の生態と、予防対処法のまとめです。個人的には特に江戸時代の子供の遊びに衝撃を受けました…。皆さんもアブラムシの生態を知ることで、より的確な対処ができるようになると思いますので、是非覚えておいていただければと思います。そんなアブラムシについての記事でした。
関連情報
植物でワクワクを| BOTANICAL BOX
世界はあなたの見たことのない植物で溢れている。
コレクター心をくすぐるカッコいい植物や、想像の斜め上をいくような珍奇な植物。
私たちは、そんな厳選した世界各国の植物をお届けし、新たな発見と感動を提供します。
| SHOP | BOTANICAL BOX(ボタニカルボックス) |
|---|---|
| 住所 |
栃木県真岡市 ※請求があった場合には遅滞なく開示いたします。 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 土日祝 |
| 代表者名 | 渡辺 京 |
| info@botanicalbox-official.com |